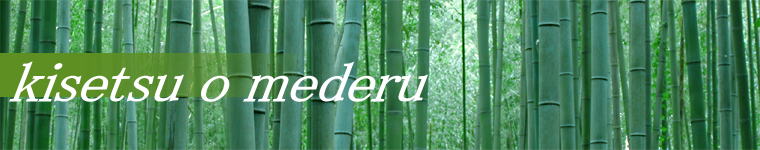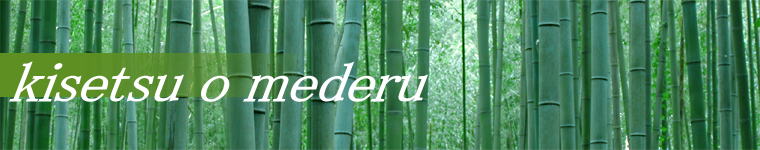花びら餅とは、
京都でお正月にだけいただく伝統の御菓子の一つで、
柔らかいお餅に京都のお雑煮に見立てた白味噌のあんをごぼうと共に求肥で包んであるお菓子です。
最近では、新年になると各和菓子司がそれぞれの志向を凝らし、店頭に並ぶようになりました。
作今、日本人としての意識が高まったのか?
こうした古きよきものに興味が注がれているように感じています。
書物でも歳時記に関するものがベストセラーになったりしていますので…。
素晴らしいことではないかと、嬉しい気持ちで見つめています。
この花びら餅のごぼうですが、
一説に、裏千家初釜の「菱葩(ひしはなびら)」を
花びら餅として菓子化したものであるからだと言われているそうです。
「菱葩」は丸く平らにした白餅に、赤い小豆汁で染めた菱形の餅を薄く作って上に重ね、
柔らかくしたふくさごぼうを二本置いて、押し鮎に見立てたもので、
鮎は年魚と書き、年始に用いられれたそうです。
押年魚は鮨鮎の尾頭を切っ取ったもので、
古くは元旦に供えると『土佐日記』にも書かれているといいます。
長寿を願う平安時代の新年行事「歯固めの儀式」を簡略化したもので、
600年にわたり宮中のおせち料理の一つと考えられてきたこの花びら餅は、
川端道喜が作って宮中に菓子を納めていたそうです。
明治時代裏千家家元十一世玄々斎が初釜のときに使うことを許可され、
新年のお菓子として使われるようになり、全国の和菓子屋でも作られるようになったという経緯があります。
花びら餅を初釜にいただくのは、茶の湯では、やはり「お約束」ということになりましょうか。
最近では求肥製が多いのですが、菊屋さんは古式のままのつき餅製のようです。
パンチがありながらお茶の滋味を引き立てるお仕立ては、いただく度にうなる美味しさです。
和菓子のブログ
|