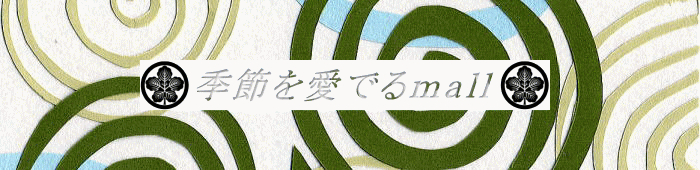お茶のお稽古を始める時、扇、ふくさ、古ぶくさ、 懐紙、楊枝
それらを入れるふくさばさみや数奇屋袋が、必要になります。
茶道とは、切っても切れない 基本的な持ち物は、お茶会へ行く時の準備でもあります。
 茶道ブログ更新しています。
茶道ブログ更新しています。| 懐紙 菓子をのせるための和紙で、席入りの前に懐中します。 茶席において出される主菓子および干菓子を取り分ける際に、客側が手元の皿代わりに用います。 この際、束のままでわさ(折り目のある側)を手前に置いて扱い、使い終わると右肩か左肩で箸を拭います。 食べ終わった後から一枚だけめくり返して、粉などが落ちないように注意して懐や袂にしまいます。 薄茶では、飲み終わった後に茶碗の飲み口を指でぬぐい、その指を懐の懐紙で清めます。 濃茶の場合は、茶碗の飲み口を直接懐紙で、または小茶巾と呼ばれる専用の布や紙でぬぐいます。 菓子を食べきれない時は、懐紙に包んで懐や袂にしまいます。 このようにお茶の席では、なくてはならないものですが、普段いつも持ち歩き、お食事のときに使ったり、こころづけを包んだり、メモ用紙として使うなど、さまざまな目的で活用できる便利なものです。 |
| 楊枝 楊枝は菓子切りといい、菓子をいただく時に使います。黒文字、象牙、金物などがあります。 茶席に入るときの必需品です。 |
| 扇子 扇子は儀礼のしるしの意味があるので、挨拶するときには必ず膝前に置くか、立って挨拶するときには右手に持ちます。 扇子は客の証でもあるので亭主は扇子を持ちません。 膝前に置いて挨拶をしたり、床点前座を拝見するのは扇子を結界かわりにし、自分自身を謙虚にするためです。 結界とは本来、仏の世界と俗界とを区別する事を意味し、結界をつくり挨拶をすませて、はじめて結界が取り除かれることになります。 扇子には男性用、女性用がありそれぞれに竹と塗りのものがありますが、区別の約束はありません。 |
| 帛紗 客が扇子を必ず手にするのと同様ふくさは亭主のしるしで客を迎える時から送り出すまで腰につけています。 点前中はこれを捌いて道具を拭き清めるのに使用します。 道具は使用する前に必ず清めてありますが、お客様の目の前でもう一度清める事でより一層の清浄感を出します。 生地は塩瀬、羽二重、斜子などがあり男性は紫、女性は朱もしくは赤を使用します。 裏千家では玄々斎宗匠以降は種々の色を使った友禅などもありますので季節や趣向によって使うのもよろしいかと思います。 寸法は男女共縦27,5cm・横28,4cmです。 |
| 古帛紗 古帛紗は裏千家で使用されます。 濃茶、茶箱、荘り物、などのお点前に用いたり、亭主は濃茶の時など楽茶碗以外は茶碗の熱が外に出るのを考慮して茶碗の下に用いて下さいとの意味を込めて古帛紗を添えて出します。 客は出された道具を拝見するときに使用し亭主への敬意を表します。又薄茶の場合でも水屋から点て出しをする時、古帛紗上に茶碗をのせて出します。手盆の失礼を避けるためです。 寸法は縦15,2cm・横15,9cmです。器物同様鑑賞の対象となるところから本来は由緒ある裂地で作られます。 |
| 数奇屋袋 数奇屋袋は懐紙入がすっぽりと収まり、持ち運びに便利で大変重宝なものです。 おけいこごとの小物入れとしておしゃれでサイズが手頃で、ぜひ持っておきたい袋物です。 懐紙入れも普段でもぜひ持っておきたいアイテムです。 |
上のようなもの達が必要になりますが、単品でお求めいただくこともできますが。↓
セットでの購入の可能です。






|
|
|
|
 茶道ブログ更新しています。
茶道ブログ更新しています。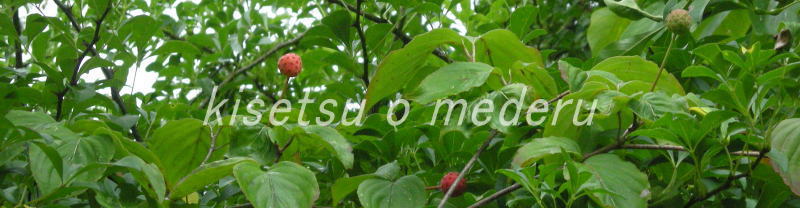 |
茶道、和菓子、お稽古日記、お気に入り 犬のある生活を中心にした ウェブサイトを展開しております。 |